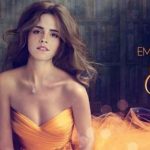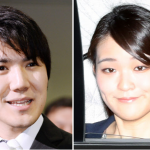*当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。
Netflixで最近「アドレセンス」を観た。
英語では「adolescence」、「青年期」「思春期」を意味し、AIに聞いたところ具体的には子供から大人へと移行する過程で成長や変化が激しい時期を指し、一般的には、10歳代から20歳代前半までを指すとのこと。
イギリス英語に惹かれてNetflixで「イギリス英語」「イギリス」と検索した結果、このドラマが「おすすめ」で出てきた。でもそんなに期待してなかった。。。
けれど、どんどん惹き込まれていき、評判が良いことがわかり嬉しいサプライズだった。
期待してなかったのに見応えがあったのだから。
この時代特有の問題を凝縮した内容で、どの国にも世代にも観る価値はあると思う。
是非観て欲しい!
英語学習として観始めたが、心を打たれた瞬間
このドラマを観始めたきっかけは、「英語のリスニング力アップになりそうだな」という軽い動機。
けれど徐々に惹き込まれ、途中から英語どころではなくなった。
もちろん、それでは意味が無いから「耳」をそば立てて会話に集中したけれど、「勉強」という意識は全く無く、純粋にこのドラマが描こうとしている事を理解しようとした。
何度も途中で「ふっとハートを掴まれるような感情が湧いた瞬間」があった。
そしてこれは単なる「サスペンス」ではなく、もっとずっと深いものが描かれているとわかった
「Don’t you even like me a bit?」に表れた孤独
印象的だったセリフはいくつもあったけれど、とりわけ胸に刺さったのが、主人公ジェイミーの「Don’t you even like me a bit?」という一言。
この問いかけには、「誰にも好かれていないのではないか?」という深い孤独が滲み出ていて、観ているこちらまで心がギュッとなった。彼が本当に求めていたのは、「何でもかんでも認めろ」と言う承認でもなく、賞賛でもなく、ただ「誰かにちゃんと好きだと言ってもらうこと」だったのでは?
日本語訳で「少しは僕のこと好き?」。この「少しは。。。」と言うところが泣かせる。
単純に「Do you like me?」「Don’t you like me ?」にしなかった理由があるような。
このセリフ自体、もちろん英語として難しく無い。
でも、ジェイミーが不安を抱き、複雑な表情を浮かべて「少しは僕のことが好きだったよね? お願い、そうだって言ってよ!」と、どうしても相手から「好きだ」という言葉を聴きたくて叫んだこのセリフは忘れることができない。
単なるサスペンスじゃない、と思い始めた数々の問題
序盤こそ「犯人は誰なのか?」というサスペンス的な要素が前面に出ていて、私も「よし、誰が犯人か当てようじゃないの」って意気込んでた。
でも観ているうちに「このドラマの本質はそこじゃない」と気づいたのよね。
ジェイミーが犯人かどうか、というのはきっかけに過ぎず、本当に描かれているのは歪んだジェンダー観、いじめ、孤立、親とのちょっとした原因でのすれ違い、しかもお互い思い合っているのに。。。
そして現代の若者が直面している「見えない闇」。
加えて私には「無関心」も描かれていると思った。
ワンカット撮影が映し出す「逃げ場のない空間」
ほぼ全編を通して長回し(ワンカット)で撮影されている演出は、観客に強烈な没入感を与えると思う。視点が切り替わらないことで、「登場人物と同じ空間に閉じ込められている」ような感覚すらあり、「これは単なるエンタメじゃないぞ」って突きつけられた感じ。
実際、本当に自分が一緒に歩いているようだったし、とにかく迷路みたいだった。普通に「あ、私この間取り覚えられないな〜」なんて思ったくらい。
また、迷路みたいに歩く演出は、このドラマの「問題の複雑さ」を表すためでは?
ジェイミーだけでなく、父・エディも“主人公”だと思う。むしろ主人公?
この物語のもうひとりの主人公は、間違いなく父親・エディだと思う。
彼は不器用で短気。でも根底には家族に対しての深い愛がある。
ドラマでは「短気」な部分を描かれてるけれど、どうでもいいところで怒鳴るわけじゃないし、理由がちゃんとある。
もちろん理由があっても怒鳴られた家族はたまったもんじゃないけれど、彼はどんなにイラついても「Sorry」とか「Thanks」とか怒鳴っている最中にもちゃんという。自分の過ちにに必ず向き合う。
そこが観ていて私は大好きでしたね。だって大事な部分を外さないから。
息子と分かり合いたいのに、どうしていいかわからない。
「いい父親」になろうと努力する姿に、観ているこちらも胸を締めつけられる。
息子の事で必死に家族を守ろうと「痩せ我慢」と思われるその姿からは「支えられるべきは父親なんじゃないか?」と思うくらいだった。そして、強さに必死で「甘えられない男性像」が描かれているのでは?と。
SNS時代のいじめと、若者を取り巻く危うさ
この作品は、現代のSNSと若者の関係性を非常にリアルに描いている。誰かを笑いものにすることが「娯楽」として拡散され、いじめが可視化されにくくなっている現状。
被害者のケイティは確かに気の毒な存在ではあるけれど、彼女自身もまた、物静かな人間を相手に「陰湿ないじめ」を繰り返していた加害者。そこに対する非難のトーンは、個人的にはもう少し強くても良かったのではと感じた。 とにかく「いじめ」が陰湿!
学校の「無関心さ」が示すもの——これも現代性?
作中で違和感を覚えたのは、生徒のひとりが亡くなったという重大な事件にもかかわらず、学校の生徒たちの多くが警察への事情聴取に不真面目で、軽口を叩いたり、悪ふざけをしていたこと。
とにかく「笑う」のよね。。普通に考えて、「人が亡くなっているのに」と怒りを覚え、とにかくイライラした場面だった。
そして同時にこれは現代の若者に見られる「他人への無関心さ」をあえて描いたのかもしれない——そんな考えもよぎった。そして全てが無意識のうちに「ゲーム感覚」になっていて「命の重みを理解していない」ことも描こうとしたのかもと。
マノスフィア・incel思想っぽさも背景にある
劇中に散りばめられていた「男性の怒り」や「承認されないことへの不満」は、現代のマノスフィア(男性至上主義ネット文化)やincel(自称「非自発的独身」)思想を意識してる。
そういう事を描いていること自体はわかったけれど、実はこれらの言葉はこのドラマを観るまでは知らなかった。やはり生の素材で英語はやるべきと思ってしまった。
これらの思想は極端で危険だけれど、その根底には「理解されなかった孤独」や「自己否定の連鎖ーフェミニズム運動で女性の地位が確率しつつある中でうまく自己表現ができない、自己肯定が低い男性たちの怒り」が潜んでいて、ドラマはその危うさに光を当てつつ、ジェイミーを通して「対話の可能性」「認め合うことの大切さ」を描いていると思う。
心理療法士の“誘導質問”みたいなやりとり、観ていて引っかかった
物語の中で心理医療法士がジェイミーに対して行う質問に、どこか「答えを誘導する」ような違和感を個人的には覚えた。
ジェイミーに「父親はどんな人か?」とやたらと聞き、父親が古臭い考えの持ち主なら「男らしくしろ、という父親の考えが影響があるのでは?」それは即ち「女性蔑視の思想も植え付けられているのでは?」と方向づけてしまうような問いかけ。観ていてこれも嫌でしたね。
役者陣の演技が支えるリアリティ
ジェイミー役の俳優オーウェン・クーパーが本作で俳優デビューとは思えないほどの自然な演技を見せており、驚かされた。ワンカット撮影の中、凄いと思う。
声変わり中? 繊細な声質もこの役にぴったりだと感じた。
また父親エディを演じたスティーヴン・グレアムは圧巻! この役の彼の英語の訛りはかなり強く、正直リスニングには苦労した。。。いや、私の英語力は元々低いから仕方ないけれど。
グレアムは、役によってアクセントを自在に変えることで有名な実力派俳優とのこと。知らなかった。。。
彼の過去作『ライン・オブ・ドゥーティー』(大好きな作品)でも難しい役を見事に演じており、今回もまた忘れられない存在感を放ってた。 実は昔の「スナッチ」という映画の「トミー役」とは気が付かなかった。
なぜこのドラマは80カ国以上で共感されたのか
「SNS時代の孤独」「SNS用語の意味の世代による使い方の相違」「親子のすれ違い」「社会の無関心」「教育の限界」「スクールカースト」「いじめでも単なるいじめじゃなくて女性が大人しい男性をバカにする構図」そして「フェミニスト運動で女性の地位は上がりつつある一方、自己肯定感が低い男性は孤立、疎外感を持ちその怒りを女性に向ける思想」
悪循環でしかない。
私は女性に対しての理解が深かまるのは良い事だと思うけど、極端な行き過ぎたフェミニズムは嫌いで、何でもかんでも女性蔑視!と言う事で逆に女性からも男性から反感買うのでは?と感じていたから、極端な現代の「マノスフィア」思想が生まれる理由、そしてSNSを通じて静かにこの思想に影響される男性への警鐘も描かれていて納得した。
——このドラマが内包するこれらのテーマが、現代のどの国にも世代にも当てはまるからだと思う。
結末は「答えを丸投げ」じゃない。ちゃんとスッキリする。
こういうドラマは観客に結論を丸投げしてスッキリしないことが多いけれど、最後にはしっかりと物語の「帰結」を描いてくれてスッキリした。
ここではネタバレになるから書けないけれど、お母さんが「適切な大人」としてお父さんをジェイミーが選んだ時に、少し意外そうにしていた「ちょっとしたシーン」の意味がわかったし、最初は英語音声だけで観ていたから分からなかったけれど、お母さんが最後のあるシーンで泣きながら、でもほんの少し笑顔を見せる理由がわかってそれもスッキリ。 あとは例の「大事な答え」も分かる。
あとは警察が踏み込んだ時のジェイミーの反応に疑問を感じていたけれど、最後にその理由がわかってスッキリした。まあ、これは刑事物を観てきた人なら分かるかも?
お母さんも、娘さん(ジェイミーのお姉さん)もとても素敵な人だった。
ラストシーンは切なかったよ。
でもここから、「家族の再生」が始まると期待した。
SNS規制? いや、それってただの「応急処置」でしょ?
SNS規制が議論になる昨今だけど、それってただの「絆創膏」。
単なる「対処法」だと個人的にいつも思う。
必要なのは、根本的な「モラル」「多様性」(胡散臭い多様性じゃない、受け入れられないって事も認める事も必要。だって多様性でしょう?)「許す強さ」「生き抜く力」を子どもたちに伝えること。
「人生はうまくいかないこともある——それでも他人や環境のせいにせず前を向いていける力」を育てること。
このドラマはその必要性を、静かに、でも確かに突きつけてきた作品でした。
*アイキャッチ画像は「Socialist Alternative」より
*リンク先はアフィリエイト広告を含みます
ExpressVPN